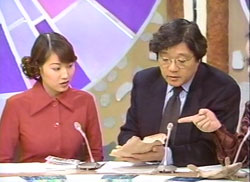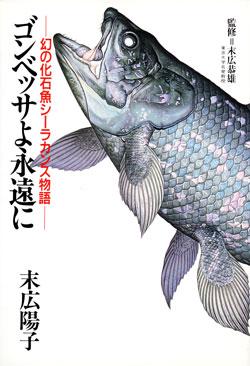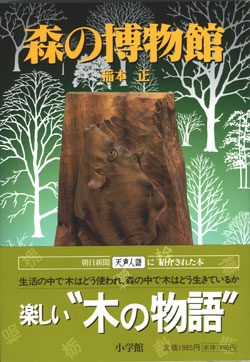|

���s���f�B�A
�ł̏Љ��t
�ؐ��̒����̍�i���e���f�B�A
�ŏЉ�Ă��������܂����B
���y�e���r�E���W�I�z
���������a�̎R�����@'07 5/31
�u����ăi�C�g�v���ŃC���^�r���[
�p�[�\�i���e�B�[�F���c��a�F
���uNHK�j���[�X�E�F�[�u�v���
'2005 7/2
�������e���r�u�y���}�Ӂv���
'98 10/27
�������e���r�u�V�����^�v���
'98 10/24
���u�����֍s�������v
�f98 9/24
��� ���|�[�^�[�F�ɓ�������
10/24���f
���u�a�̎R�i�E�v�@'97 5/9
�l�ɋZ����u���̒B�l�����v
���|�[�^�[�F����˗��q
���ǔ��e���r�u���ق�킩
�e���r�v��ށ@'97 5�23
���a�̎R�e���r '97 6/24
�u�R�~���j�e�B�[�T�����v����@
���s�u�����u�g�D�i�C�Q�v'97
'971/28���
�@ �R�{�W��ēE�ؓ�������
���y�V����G��
�ł̏Љ��z
�������V�� �n��j���[�X
�u�����܂��I�v�@'07 3/1
�������V�� �n��j���[�X
�u���������v�@'07 3/29
����I�B�V���@
�u��炵�̐��E��Y�@��v�@
��ށF���F�� ' 06/9/23
����l�Ё@�e���� �e���������� '04 2/21
�u���ӂ̑��`�v
���Y�o�V���@�I���� '99 1/22
�u�̉�����ő��������v
���x�m�� �r�v�f�e�l�@'98
�@ �ؐ��̐��E�A��
�����w�كT���C�@'97 5/15
�g�s�b�N�X[���̋�����]
���і�O�ω�@�G��
�X
'97�t��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�ƑΘb�����v
���I�ɖ���
���ޒ����W�A�A
'96 10/6
�����l�o�� '96 11/9
���R�̑���A�A '99 1/1
��Patchwark
�uHOT INTERVIEW�v '96 4/19
�������V���@�}���I����炵�̏��
�@ �X�p�E�H�[�N�@�V�؏����
�����w�� �u�X�̔����فv
��{�����@'94 12/6
���R�ƌk�J�� �E�b�f�B�[���C�t
'96 12 No.68�t�B�b�V���J�[�r���O
����l�� �e���� �e���������� '92 5/26�@
�`���� �f������������ �u�t�B�b�V���J�[�r���O�v
���R�ƌk�J�� �k���t�B�b�V���O
'89 2.�@No.5�`8�t�B�b�V���r �� �O
�A��
���R�ƌk�J�� �k���t�B�b�V���O
'88 No.4 �t�B�b�V���J�[�r���O
�@
�@
�@
�@
|
�ؐ��̂���I�u���O
<
new page ������
>
��602�� �l�ɋZ����I���̒B�l�����i23�j���|�[�^�[�F����˗��q 1997.05.09
�@

�@
�e���r�a�̎R�ԑg�u�킩��܃i�E�v�l�ɋZ����I���̒B�l�����ɂėؐ��̖ؒ������Љ��
�܂����B
�H�[�͓��{��̔~�̗��ŗL���ȓ암�쑺�ӈ�ɍ\���A���傤�ǔ~�̍���Y���T����
�Ő����Ɏ�ނƂȂ��
�����B�a�̎R�ł͐F��ȕ�������Ă���E�l��A�[�`�X�g�����͂������܂��B���̒��ł������ ����
�łɂȂ��ς��_�l�Ƃ��Ď��グ�Ă��������܂����B
�@�@�@�@�@�@
|

�F��ȍޗ��ƂȂ�̒��œ��ɍS�����ނ����o
���ǂ̂悤�Ȏg����������̂��������B

�ނ̑I�肪���܂�؎������Ă��狛�̌`�ɑы�
�Ŕ҂��Ă����B

�q�ɂ̓V��ɒ����قǑ�ʂ̍ނ������Ă�����
��
�ɂȂ�̂͂����킸���ł��B

����Ȓ��ł����ɂ���ȕ������������낢��i��
�o�����ł��ƈ�ʂ̐l�ł͒m��Ȃ��悤�Ȃ���
������B

�����V�؏�̂Ƃ���V���E���[���ɃA�N�A���E��
�I�ȕ��͋C�ō�i���W������Ă��܂��B
��͒W�����A�����C�����R�[�i�[�ł��B


�N�X�Œ������A���J�P

�k�O�I�[�i�[���R����Ɠ������̂��Ƃ��n�m��
�Ă��Ď��̍�i�̂��Ƃ��悭�������ĉ������Ă�
���\������В��̑��䂳��B
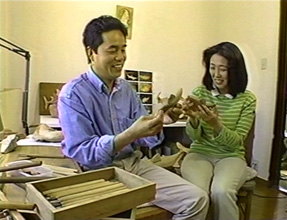
�������ꂽ��i�߂Ă���ƂȂ����S���a�݂�
���B��葽���̐l�Ɍ��Ă��������Ƃ���ɂ����
�{�����܂��B
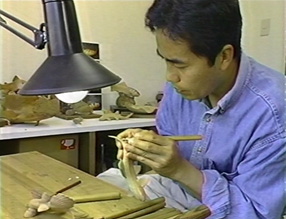
�@
�W���͂�����������Ƃ͐[��ɂ܂ŋy�ԁB |
�ޗ��I�т��犮���܂ŎB�e�������I�����܂����B
����̎�ނɓ�����ԑg�f�B���N�^�[�̓��䂳��ɂ͑�ς�����ɂȂ�܂����B���ɎB�e�ɂ�
�͂����Ă�
��������i�����ɂ��ꂢ�Ɏʂ��Ă��܂����B���ꂩ�烊�|�[�^�[�̐���Ƃ��y������炢���ł�����
�Ƃǂ����L��������܂����B
2007.12.31���ݎ��̍�i���W������Ă����k�O�V���[���[���̓��j���[�A������Ă��邽��
�����i����
�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����Ƃ����������������B
�@
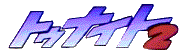 1997.01.28
1997.01.28
�e���r�����u�g�D�i�C�g�Q�v�̕������ނ̈˗�������܂����B
�g�D�i�C�g�Q�͐[��̏��o���G�e�B�[���ԑg�Ŏi��́u�u���[�^�X�v�u�^�[�U���v�u�K���o�[�v
�ȂNJe����
�ҏW�����C����ΐ쎟�Y�A�����Č��I�ȃ��|�[�^�[�Ƃ��ĉʊ��Ɏ��g��ł���͎̂R�{�L��ēł���B
�@�@�@�@�@�@�@
 
�L���X�^�[�̐ΐ쎟�Y����ƎR�{�L��ē�
��i�̃J���n�M���X�^�W�I�Ɏ������ݖؒ����ɂ��ĔM�ق�U�邤�ēB
�@

�@
��ނ͓��A��̋��s�X�P�W���[���ł܂��͎��̍�i���W�܂��Ă��铌���V�؏�̖^�V��
�[���[���ō�i��
�B�e�A���ꂩ���s�@�Řa�̎R���͓�I���l�ɁB�Ԃŏo�}���@�ޗނ�ςݍ��݂����������悭�s������
�����ق֗��ꍞ�݊ώ@�V�[�����B��B
�����̃p�^�[���Ȃ̂ł�����i�������Ƃ���ƍ�Ə�i�����J�b�g������e��肵����
����Ƃ���j
�����Ď���̈ꎺ�i�d�グ�������肷��Ƃ���j����ӏ��ɂȂ����ߎ�ނ̂Ƃ��͂�����ςȂ̂ł��B
 
 
 
���ꂻ���Œ���Ȃ��ċ�킷��ēƖؓ������炳��
�؍ނ�u���q�ɂ͂���ȂɍL���͂Ȃ��̂Ńr���̂悤�ɐςݏグ���ނ����āu����[���I����
�S������́H�v
�ƕ����ꂽ�̂ł������͎g���镔���͂��̔����ɂ������Ȃ��̂ł���Ɛ����B
���Ă��������ǂ̂悤�ɐ��삵�Ă���̂����ۂɍ�Ƃ���������ƂƂ��ɊēƖؓ�������
����̂������
���̌����Ă����������ƂɂȂ�N�X�̖ŃT�������Ă����������Ƃɂ��܂����B
���̌`�ɃJ�b�g���Ă������̂���X�^�[�g�����̂ł����p���ۂ���藎�Ƃ��Ƃ��납�炷�łɈ���
�ꓬ�B
����Ə_�炩���ނ�p�ӂ��Ă������ق����悩������������܂���ˁB
�ł��N�X�̃c���ƕ@��˂��������������ɏ[�����Ă����ɂ����������Ă���ċC���ɂȂ肨����͋������
���ɂ���Ȃ�Ɋy����ł����������悤�ł��B���^���I�Ղɍ����|�����Ă����Ƃ���ŋA��̔�s�@�̎��Ԃ�
�����Ă��܂����B
�f�B���N�^�[�@�u�ē��@�I�@�������Ԃ�����܂���B�v
�ē@�u����Ƒ҂悤�Ɍ����Ƃ��I�v
�����}���Ȃ��ẮB���Ԃ��肬��܂ŔS�������ߋA��̔�s�@�ɊԂɍ������ǂ�����Ԃ܂��
�������Ȃ�Ƃ�
��`�Ɋ��荞�݃Z�[�t�ł����B �ǂ�������J�l�ł����B
�ĂȂ킯�Ńg�D�i�C�g�Q�̎��^�͖����I��������e���r�Ŕq�������Ă����������ƂɂȂ�܂����B
�@�@�@�@�@�@
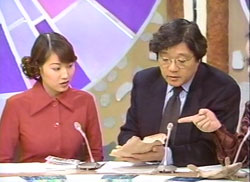 
���Ƃ����̌`�ɂ������̂��X�^�W�I�Ɏ����A�菭���������Ă݂���L��ē�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@
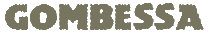 �S���x�b�T�ɖ�������
1992.09.24 �S���x�b�T�ɖ�������
1992.09.24
�@
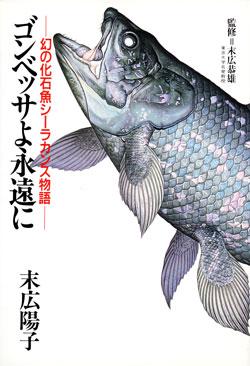 |
�S���x�b�T�Ƃ̓V�[���[�J���X�̐����n�R�����������ӂł̌Ăі�
�Ţ�g���Ȃ����v�Ƃ����Ӗ��ł����������̉��l�����炩�ɂȂ荂�l�Ŏ�������悤�ɂȂ������݂ł́u�K�^���Ăԋ��v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ��Ă���B
�@���ފw�Җ��L���Y���𒆐S�Ƃ���V�[���[�J���X�w�p�������ɂ����{�̑�ꍆ�ߊl���P�X�W�P�N�A
�����ĂW�U�N�ɂ͐��E�Ŏn�߂ĊC���V�j�̎B�e�ɐ��������B
�@�{���͔����̂�����������{���̊���܂ŁA���ފw�҂ł���̖��L���Y���m�̒������L�z�q�������̎v�������߂ĒԂ�Ȋw�h�L�������g�ł���B
�@
�@ |
|
�����̃��f���Ƃ���
1981�N12��31����P���ߊl�̂��̂͑̒��P�V�V�����A�d���W�T�s�Ɨ��h�Ȃ��̂ŔN�������Ď����A����
�V�[���[�J���X�̓}�X�R�~�ő�X�I�Ɏ��グ���܂����B ��ʌ��J�͐��C�̃t�B�b�V���O�V���E����
�Ɋe�n�ōs��ꂽ�����ۂɎ��������邱��
���o���Ă��Ȃ������̂œ������{�ŗB��t�Z�W�{����Ă���Ƃ�
�����s��݂��胉���h
�C�������قɑ����^�Ԃ��ƂɂȂ�܂����B
���̎����W�{��1966�N12���ɃR���������ŕߊl����Ă��̂ŁA1967�N�t�����X���{���
�����̓ǔ��V����
�Ў吳�͏����Y���Ɋ��ꂽ���̂ł��B
�̒��P�T�U�����E�̏d�T�T�����̋��̂̓z���}�����Ђ��ɂ���Ă͂�����̂̍�������������
�ɕ���ꂽ
�̂͂܂��ɐ��������̑㖼���ɑ����������̕��e���炵�ċ����Ƌ��ɐ��������Ñ㋛�ł��邱�Ƃ��m�F��
����
�̂ł���B�Ɠ����ɒ����̃��f���Ƃ��ĕs���͂Ȃ��B�ō��̂��̂��o�������Ɠ��S�͔M�����̂�������
���܂����B���������ƍ�i�Ƃ��ĊF�l�̑O�ł���I�ڂł���Ǝv���Ă��܂��B

��݂��胉���h�C�������ٓ��V�[���[�J���X�W���R�[�i�[�ɂ�
1992.09.24
�@


�ǂ����Ă����ނɂ͌����Ȃ��悤�Ȋe�h

���h�̐�[�ɂ���ɏ����ȕh������̂������ł��B �@
���̉t�Z�W�{�͂�݂��胉���h�C�������ق���2001�N3������T���V���C�����ې������Ɉڂ���W�����ꂽ
����2003�N3��21����艺�֎s���C�����Ō��݈�ʌ��J����Ă��܂��B �@
�@
�X�̔�����
�����̒��Ŗ͂ǂ��g���A�X�̒��Ŗ͂ǂ������邩
��{�����@���w�ف@�a�U
|
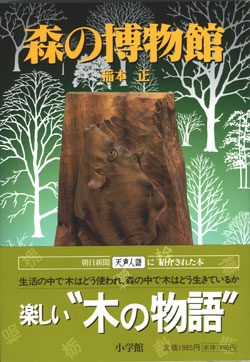
�\���ɖؒ��J���n�M���ڂ��Ă��������܂����B
|
�@
���҂͍H�|�Ƃł����I�[�N�E�r���b
�W��ɂ̈�{�����B
�{���͍L�t����j�t���Ȃǂ̖������̂Ȃ��łǂ��g���Ă��邩�A�܂��X�̂Ȃ��Ŗ�
�ǂ������Ă��邩��
���Ă̘b�A�������ɂ���炩����ꂽ�l�X�ȍH�|�i�Ȃǂ��ʐ^
�ƂƂ��Ɉ���̖{�ɂ܂Ƃ߂��Ė�
�D���Ȃ��̂ɂƂ��Ă͔��ɋ����𒍂������̂������B
�@

��̃y�[�W�ł̓C�V�_�C�ƃj�W�}�X�̍�i���f�ڂ���Ă��܂��B
�@
�e�ގ�ʂɐ�����p�r�A��i�ȂǏЉ��Ă���u�̕����v�Ƃ������̂���葽���m�邫��������
�Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
<
new page ������
>
|
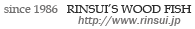










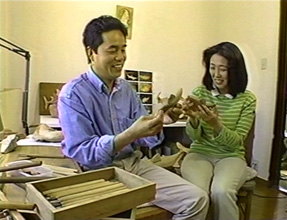
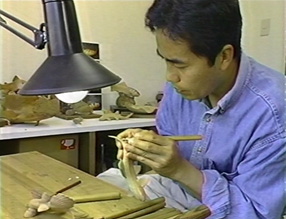
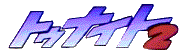 1997.01.28
1997.01.28